みなさん、こんにちは。
早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座
学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座
慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座
日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座
お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座
東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座
でおなじみの「受験対話」総合研究所です。
文学部の1年生のための「日本語」実践講座での話!
本日は、文学部の学生のための「文章クラス」に、先輩が遊びに来てくれて、
ゼミの話と文章の話をしてくれました。

「赤ちゃんから大人まで――こころの成長を見つめる学び」
こんにちは。私は文学部で、心理学のゼミに所属しています。
みなさんは、「こころ」って聞くと、どんなことを思い浮かべますか?
私たちのゼミでは、その「こころ」が、赤ちゃんのころから大人になるまで、どのように育っていくのかを学んでいます。特に、家族との関係の中で「こころ」がどう形づくられていくのかを、心理学や精神分析の視点から考えていくんです。
■「赤ちゃんのこころ」を観察する授業
私たちの研究会では、実際の家庭を訪問して、赤ちゃんとお母さんの関わりを観察するという、とても貴重な経験をしています。
たとえば、最初は表情も少なく、泣くことでしか気持ちを伝えられなかった赤ちゃんが、少しずつ笑ったり、指さしたり、やがて言葉を話せるようになっていく。その変化を、私たちは毎回の訪問で少しずつ見ていくんです。
家庭によって親子関係のかたちはさまざまです。あるお母さんは、少し心配性で、いつも赤ちゃんを抱っこしています。別のお母さんは、のびのび育てるタイプ。
同じように見えても、赤ちゃんの反応が全然違う。
授業では、その映像をみんなで見ながら「このとき赤ちゃんはどう感じているんだろう?」と意見を出し合います。学生同士でも見方が違うのが面白くて、「人のこころって深いな」と実感します。
■「こころの問題」を自分のテーマで研究
もう一つのゼミ活動では、メンタルヘルスをテーマに、学生がそれぞれ自由に研究を進めています。
たとえば、「幸福とは何か」を考える人もいれば、「強迫性障害」や「SNSとのつき合い方」をテーマにする人もいます。
毎週、研究の途中経過を発表して、先生や仲間から意見をもらいます。議論を重ねるうちに、自分の考えがどんどん深まっていくんです。
大学生は、自分の将来や人間関係について悩むことも多い時期です。そうした中で、自分の「こころ」と向き合う時間を持てるのは、このゼミの大きな魅力だと思います。実際に、自分の体験をもとにテーマを決める学生も多くいます。
■学びを通して見えてくるもの
赤ちゃんの観察を通して感じたのは、「こころ」は生まれつきのものではなく、人との関わりの中で育つということです。
また、メンタルヘルスの研究を通して、「自分の心を理解することが、他人を理解する第一歩なんだ」と気づきました。
教授はよくおっしゃいます。
「研究会は、知識を得るだけの場ではなく、自分自身と向き合い、人を理解する練習の場です」
実際、卒業後の進路もさまざまで、臨床心理士として働く人もいれば、公務員や会社員、学校の先生になる人もいます。どんな道に進んでも、人の気持ちを理解する力はきっと役に立つと思います。
もしみなさんが、「人のこころに興味がある」「子どもの成長や家族の関係を学びたい」と思うなら、きっとこの研究室は楽しいと思います。
教科書では学べない“人のあたたかさ”や“こころの不思議さ”を、実際に体験しながら学べる場所です。
故事・名言をたくさん仕入れてください!
ここからは、私の「文章修業」から、アドバイスをします。
日本語は、その発達の途中で、中国から文字を輸入しているので、
むずかしい漢語や古い中国の故事・歴史から生まれた特殊な言葉が多いですよね。
そして昔は、こういう看護の素養が、文章を書くための不可欠の要件とされていました。
この点、私はあまり大きな顔はできません。
中学、高校時代、漢文が嫌いで、怠けていたため、入試でも苦労をし、
漢語のボキャブラリーが、きわめて貧弱なのです。
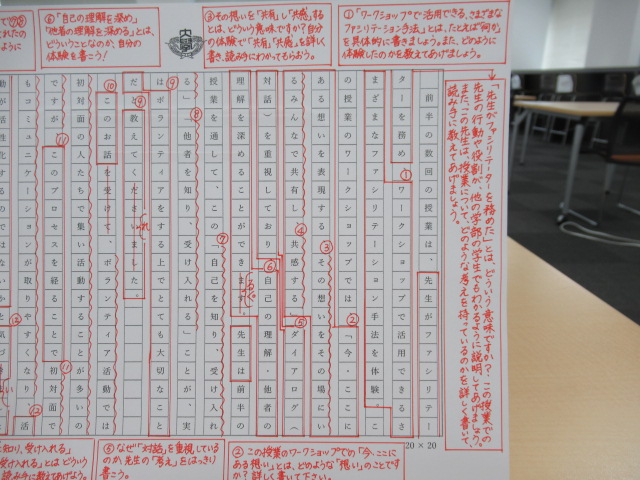
今は、日常の言葉の中での看護のウエイトは、だいぶ薄れましたが、
私のゼミ生たちの書く文章には、時々、かなりむずかしい言葉が使われたりします。
たとえば、「蟷螂の斧」「「臥薪嘗胆」「百年河清」「刎頸の交わり」「合従連衡」
「傍若無人」「金城湯池」「四面楚歌」「曲学阿世」「羊頭狗肉」「呉越同舟」
などが良く出てきます。これらの言葉は、適切な箇所に巧みに用いられると、
文章にしまりを与え、気のきいた感じをあたえるものです。
たとえば、「隗より始めよ」という言葉があります。
これは古い中国の書にあるものですが、もともとの意味は、(省略)
それが転じて、「事を起こすには、まず自分自身から着手せよ」という意味になったそうです。
この言葉を一つ覚えていれば、たとえば、何か将来の計画などについての論文や作文を書く場合、
結論の部分に「~いずれによ、まず隗より始めよのたとえ通り、自分自身が先んじて、
第一歩を踏み出す必要があります」と書くこともできます。
一年生のみなさん、故事・名言に強くなってください!
2月生:東京大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年
●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。
●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)
●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど
有名選手を取材してきました。
「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を
育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時
に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。
マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の
文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。東京大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。
【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】
確かに、今はネット時代と言われています。
トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。
しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。
新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。
まだマスコミには底力があるのです。
僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。
そこに人生が凝縮されているからです。
僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)
マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。
門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。
(故西村欣也氏・記)
■2月生
■個別指導(オンライン) 1回 80分
■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)
■まずは、お問い合わせください。






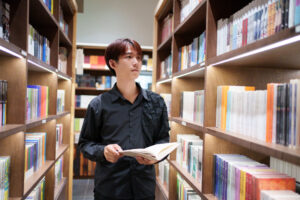




コメント