みなさん、こんにちは。
早稲田大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座
学習院女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座
慶應義塾大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座
日本女子大学の学生ための就職準備「日本語」実践講座
お茶の水女子大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座
東京大学の学生のための就職準備「日本語」実践講座
でおなじみの「受験対話」総合研究所です。
看護学部の1年生のための「日本語」実践講座での話!
本日は、看護学部の学生のための「文章クラス」に、先輩が遊びに来てくれました。
さっそく、内容を紹介しましょう。

― 慢性期・終末期のケアと、心に寄り添う看護 ―
みなさん、入学して、看護学部での新しい生活が始まり半年が過ぎました。
みなさんは、どのような感想をお持ちでしょうか?
私は、いま4年生で、「慢性期・終末期の患者さんへのケア」をテーマにしたプロジェクトで活動しています。
この分野は、体のケアだけでなく、「心のケア」――つまりスピリチュアルケアを大切にしているところが特徴なんです。
■ 「スピリチュアルペイン」って知っていますか?
たとえば、ある患者さんが、こんなふうに言ったとします。
「なんで自分は、こんな病気になっちゃったんだろう」
「自分の人生って、いったい何だったんだろう」
こういう“心の痛み”を「スピリチュアルペイン」と呼びます。
病気による体の痛みだけじゃなく、生き方や人生そのものに関わる苦しみです。
初めてこの言葉を、患者さんから聞いたとき、私は正直、どうしたらいいのか分かりませんでした。
「励ませばいいの?」「黙って聞くべき?」――答えがすぐに出ないんです。
でも、医療に関わる者として、避けて通れないテーマなんだと気づきました。
■ 学びは「現場」と「人」から始まる
私たちのプロジェクトでは、まず本を読んだり、実際に患者さんの自助会(じじょかい)や、
スピリチュアルケアワーカーの集まりに参加したりします。
現場で、患者さんや支援者の方たちの言葉に耳を傾けるんです。
ある時、末期がんの患者さんがこんな話をしてくれました。
「病気になって、家族に迷惑をかけた。でも、だからこそ“ありがとう”って言えるようになった気がする」
――その言葉を聞いたとき、私は涙が出そうになりました。
“痛み”の中にも“気づき”がある。
それを支えるのが、私たち看護の仕事なんだと感じた瞬間でした。
■ 「自分でテーマを見つける」ことの大切さ
私たちの先生はいつも言います。
「手取り足取り教えられるのを待つんじゃなくて、自分で考える力を持ちなさい」と。
私の同期のひとりは、先生から英語の論文を渡されたその週に、全部翻訳してきました。
次の春には、なんとその内容を踏まえて、自分の意見を学会で発表!
また、別の仲間は、患者さんの教育資料をつくって、実際の病棟で患者さんを相手にプレゼンしました。
「患者さんに分かりやすい説明をするのって、こんなに難しいんだ!」と話していました。
みんなそれぞれ、自分の“関心のあること”を見つけて、形にしていくんです。
ここが、この学部の一番の魅力だと私は思います。
■ 看護で学ぶ「考え続ける力」
この学部は、「慢性期」や「終末期」という、人生の最終段階をどう支えるかを見つめ直す場所です。
医療技術だけでなく、「人間とは何か」「生きるってどういうことか」を問い続ける学びなんです。
卒業してからも、ここで考えたテーマはずっと心に残ります。
それは、答えのない問いを抱えながら、それでも寄り添い、支える――そんな看護の原点を学ぶ時間だからです。
■ 最後に
これからみなさんは、教科書の中だけでは学べないことを、たくさん経験すると思います。
悩むこともあるでしょう。
でも、その悩みこそが、看護師としての成長の証なんです。
私たちも、最初はみんな迷っていました。
どうか焦らずに、一歩ずつ、自分の“看護観”を育てていってください。
私たちも、後輩のみなさんと一緒に学び、考え続けたいと思っています。
これから一緒に、心のケアを学んでいきましょう。
「看護の修業」と「文章の修業」!
この講座で学んできた「文章の修業」にゴールはありません。
勉強すればするほど、奥が深くなります。
文章には、書く人、一人ひとりの考え方の違い、表現の違いが出てきます。
これが文章の個性です。
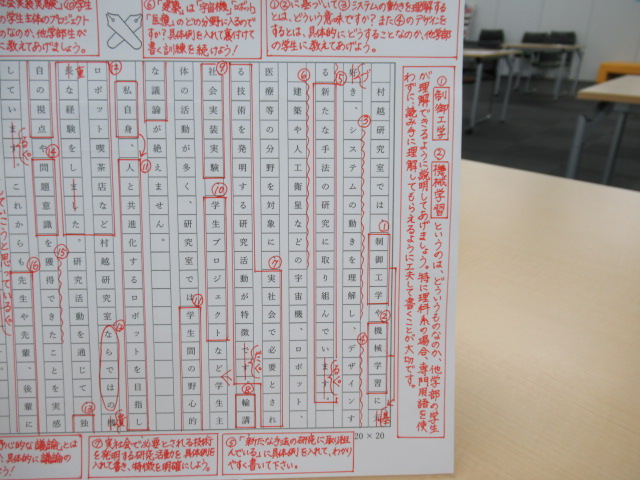
「すばらしい」といわれる文章ほど、この個性がくっきりて出ます。
文章の勉強は、いわば、この個性をいかに磨くかということでもあります。
個性を磨くことは、人間を磨くことに通じます。
文章の修業は、だからこそ奥が深く、尊いのです。
学ぶ人を引き付けて離さないのです。
「文章の道」と「看護の道」って、本当に似ていると思います。
看護学部の学生には、「文章修業」がとても大切なのだと、
四年生になったいま、あらためて私は思います。
みなさん、がんばってください。
4月生:慶應義塾大学の学生のための「マスコミ合格・添削スタート講座」オンライン

●故西村欣也氏 ●元朝日新聞編集委員 ●五輪取材経験7回・プロ野球取材30年
●朝日新聞スポーツ面に、署名入り記事「EYE西村欣也」を20年執筆してきた。
●著書 朝日新聞が伝えたプロ野球(小学館) 神の領域を覗いたアスリート(朝日新書)
●イチロー、王貞治、長嶋茂雄、清水宏保、橋本聖子、ダン・ジャンセン、ボブ・ヘイズなど
有名選手を取材してきました。
「受験対話」総合研究所では、26年前から、西村欣也氏の文章を使って、「大学生のことば」を
育ててきました。大学に入学する前から、「自分のことば」を育てる努力を始めると、就職活動時
に、あなたの「自己PR」を読んだ採用担当者から、「キミに会って、話をしてみたい」と連絡がきます。
マスコミをはじめ一流企業の担当者から、「会って、話をしたい」と言ってもらえるように、西村氏の
文章を使い、君に合わせたカリキュラムで授業を行います。慶應義塾大学の学生諸君、楽しみにしていて下さい。
【故西村欣也氏からあなたへのメッセージ】
確かに、今はネット時代と言われています。
トランプ大統領のツイートに、世界が右往左往しています。
しかし、ニューヨークタイムズなどは言論で、論陣を張り、世論の支持を得ています。
新聞だけではありません。CNNなども、トランプに「フェークニュース」と呼ばれても、事実を伝えています。
まだマスコミには底力があるのです。
僕は、主にスポーツを取材してきましたが、ニューヨークタイムズの新人記者はまずスポーツ部門に配属されます。
そこに人生が凝縮されているからです。
僕は、朝日新聞で長年、小論文の採点面接をしてきました。(やらされてきました)
マスコミ受験には、特に「書く力」が問われます。
門は狭いですが、今までの経験を生かして、スタートラインにつきたいと思う学生のアシストができれば、と思います。
(故西村欣也氏・記)
■4月生
■個別指導(オンライン) 1回 80分
■費用 スタート講座 入会金:15000円 月謝22000円(消費税込・教材費含)
■まずは、お問い合わせください。



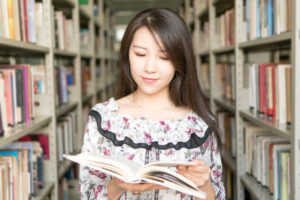







コメント